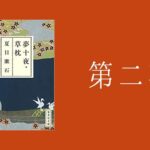『門』の紹介
『門』は、明治43年3月から同年6月まで、朝日新聞に連載された夏目漱石の長編小説です。
『三四郎』『それから』に続く、漱石前期三部作の最後の作品です。
親友の妻と結婚した主人公・宗助が、罪悪感に苛まれ、救いを求めていく様子を描いています。
ここでは、そんな『門』のあらすじ・解説・感想までをまとめました。
『門』ーあらすじ
東京の役所に勤める野中宗助は、崖の下の借家で、妻・お米と暮らしています。
ひっそりと日々を送る宗助とお米でしたが、宗助の実弟・小六を引き取ることになり、夫婦の日常は変化を迎えます。
ある日、宗助はお米との会話の中で、子供の話題に触れます。
するとお米は、自分には子供ができないと泣き出し、原因として「かつて人に対して済まないことをしたからだ」と占い師に言われていた事実を宗助に明かします。
お米は元々、宗助の大学時代の親友・安井の妻であり、宗助は安井を裏切ってお米を得たのでした。
ある時、宗助は借家の家主・坂井から、帰国した坂井の弟と、坂井の弟の友人との食事に誘われます。
坂井の弟の友人が安井だと知った宗助は、罪の意識に苦しみます。
救いを求めて鎌倉へ参禅に向かう宗助ですが、悟りは開けず、自分は門を通る人でも通らずに済む人でもなく、門の下に立ちすくんで日暮を待つ不孝な人だと考えるのでした。
東京に戻った宗助は、坂井の弟と安井が既に出国したと聞き安堵します。
月が変わり、宗助は昇給し、小六は坂井家の書生になり、夫婦の日常は小康を得ます。
春の到来を喜ぶお米に、「でもまたじき冬になるよ」と宗助は答えるのでした。
『門』ー概要
| 物語の主人公 | 野中宗助:東京の役所勤め。元々は東京の資産家の息子で、京都の大学に通っていたが、御米を得たことで中退。 |
| 物語の重要人物 | ・お米:宗助の妻。早産などで三度子供を失っている。 ・安井:宗助の大学時代の親友。御米の元夫。 |
| 主な舞台 | 東京、鎌倉 |
| 時代背景 | 明治42年~明治43年 ※作品冒頭で明治42年10月に起きた伊藤博文射殺の号外に関する会話があることから、明治42年秋〜明治43年春にかけての物語だと推測されます。 |
| 作者 | 夏目漱石 |
『門』―解説(考察)
・『三四郎』『それから』との関連性
『門』は、『三四郎』『それから』に続く漱石前期三部作の最後の作品です。
これらの三作品は、登場人物も舞台も全て異なる、独立した作品です。
しかし、三作品にはいくつかの関連性があり、『門』では下記の二点を見ていくことができます。
- 主人公像の継承
- 話のテーマの継承
それぞれ、順に考察していきたいと思います。
1.主人公像の継承
『門』の主人公・宗助は、どこか諦観しているような、覇気を感じさせない人物です。
それは、宗助の叔母が宗助の様子について、お爺さんのように老けていると評していることからも読み取れます。
しかし、学生時代の宗助は、友人が多く、楽天的で、未来が開けている若者でした。
目の前の新しい世界に触れ、期待や希望を感じる一方で、未来が確としていない様子は、『三四郎』の主人公・三四郎の人物像と共通するところがあります。
宗助もまた、三四郎の延長上に生み出された人物であり、漱石が前期三部作の基軸に主人公像の継承性を意識していたであろうことが窺えます。
2.話のテーマの継承
前期三部作の二作目にあたる『それから』は、主人公・長井代助が、友人の妻・三千代と生きていく決意をするまでを描いた作品です。
代助の選んだ未来は、まさに『門』の宗助が選んだ道です。
『門』は、宗助が親友からお米を奪った後の様を描いた作品であり、『それから』のテーマの継承は明らかと言えるでしょう。
また、『それから』と『門』は、印象的な色彩表現にも関連性を見出すことができます。
『それから』のクライマックスでは、代助がそれまでの豊かな生活や家族を捨て、職を探しに町へ飛び出し、赤く染まった狂気の世界に堕ちていく様子が描かれます。
「ああ動く。世の中が動く」とはたの人に聞こえるように言った。彼の頭は電車の速力をもって回転しだした。回転するにしたがって火のようにほてってきた。(中略)
たちまち赤い郵便筒が目についた。(中略)傘屋の看板に、赤い蝙蝠傘を四つ重ねて高くつるしてあった。(中略)四つ角に、大きい真っ赤な風船玉を売ってるものがあった。(中略)小包郵便を載せた赤い車がはっと電車とすれちがうとき、また代助の頭の中に吸い込まれた。煙草屋の暖簾が赤かった。売出しの旗も赤かった。電柱が赤かった。赤ペンキの看板がそれから、それへと続いた。しまいには世の中が真っ赤になった。
夏目漱石『それから』,角川文庫,1953年初版,297~298頁
『それから』において、【赤】は代助の不安を象徴するカラーです。
そして、『門』では、学生時代の宗助がお米と初めて交わした談話を回想するシーンで、以下の表現が見られます。
宗助はきわめて短いその時の談話を、いちいち思い浮かべるたびに、そのいちいちが、ほとんど無着色といっていいほどに、平淡であったことを認めた。そうして、かく透明な声が、二人の未来を、そうしてああまっかに、塗りつけたかを不思議に思った。今では赤い色が日を経て昔の鮮やかさを失っていた。互いをやきこがした炎は、しぜんと変色して黒くなっていた。二人の生活はかようにして暗いなかに沈んでいた。
夏目漱石『門』,角川文庫,1951年初版,164頁
『それから』の代助の頭の中を焼き尽くした【赤】は、『門』ではまるで焼け焦げた後のような【黒】になって、宗助の生を暗いものにしています。
【赤】から【黒】という色彩表現の変化も、『門』が『それから』の世界を継承していることを示す一つの証であると考えます。
・『門』の冒頭部分が示すもの
『門』では、縁側での野中夫婦の会話シーンがしばしば描かれます。
縁側での夫婦の会話から作品が始まり、縁側で宗助が「うん、しかしまたじきに冬になるよ」と発するシーンで作品が終わります。
縁側で始まり、縁側で終わる作品構造を見ても、縁側での会話シーンは重要な役割を担っているのではないかと思われます。
ここでは、冒頭部分の内容に焦点を当てて、考察を進めたいと思います。
作品冒頭部分の縁側での宗助とお米の会話シーンは、
宗助にこれから起こる展開の暗示・宗助の置かれている状況の暗示
であると考えます。
冒頭の宗助とお米の会話は極めて日常的で、とりとめのない内容です。
すると宗助は肱ではさんだ頭を少しもたげて、
「どうも字というものは不思議だよ」とはじめて細君の顔を見た。
「なぜ」
「なぜって、いくらやさしい字でも、こりゃ変だと思って疑りだすとわからなくなる。このあいだも今日の今の字でたいへん迷った。紙の上へちゃんと書いてみて、じっとながめていると、なんだか違ったような気がする。夏目漱石『門』,角川文庫,1951年初版,10頁
いわゆる漢字のゲシュタルト崩壊を言っているのだと思いますが、他にいくつもゲシュタルト崩壊が起こりやすい漢字がある中で、宗助が引き合いに出しているのが「今」です。
「今」がわからなくなる、「今」の崩壊は、お米とひっそりと生活を送る宗助の今の日常が、安井の消息を耳にしたことで崩れていくことを暗示しているように思われます。
また、縁側から繋がっていく情景描写として、次の表現があります。
針箱と糸屑の上を飛び越すようにまたいで、茶の間の襖をあけると、すぐ座敷である。南が玄関でふさがれているので、突き当たりの障子が、日向から急にはいって来た眸には、うそ寒く映った。そこをあけると、廂にせまるような勾配の崖が、縁鼻からそびえているので、朝のうちは当たってしかるべきはずの日も容易に影を落とさない。崖には草がはえている。下からして一側も石で畳んでないから、いつくずれるかわからないおそれがあるのだけれども、不思議にまだくずれたことがないそうで、そのためか家主も長いあいだ昔のままにしてほうってある。もっとも元はいちめんの竹藪だったとかで、それを切り開く時に根だけは掘り返さずに土堤の中に埋めておいたから、地は存外しまっていますからねと、町内に二十年も住んでいる八百屋の爺が、勝手口でわざわざ説明してくれたことがある。その時宗助はだって根が残ってれば、また竹がはえて藪になりそうなものじゃないかと聞き返してみた。すると爺は、それがね、ああ切り開かれてみると、そううまくゆくもんじゃありませんよ。かし崖だけは大丈夫です。どんなことがあったって壊えっこはねえんだからと、あたかも自分のものを弁護でもするように力んで帰っていった。
夏目漱石『門』,角川文庫,1951年初版,10頁~11頁
宗助とお米が住む借家の座敷は、すぐそばにある崖に遮られて、日の光が容易に届きません。
また、その崖は補強もされておらず、いつ崩れるかもわからない見た目をしています。
夫婦がいるところは、薄暗く、すぐ側には崩壊を予期させるものが迫っているのです。
これは、二人が置かれている状況の不安定さをそのまま象徴している描写だと考えます。
一方で、「地は存外しまっていますからね」、「どんなことがあったって壊えっこはねえ」という爺の言葉に表れるように、宗助とお米の愛の強固さ、二人の関係性の深さも象徴されていると考えます。
一見、何気ない夫婦の会話のシーンで始まる冒頭は、『門』の主人公の現状と未来を読者に暗示させる、非常に重要な部分であると考えることができるでしょう。
・「結核性の恐ろしいもの」とは何か?
『門』第十六章は、宗助が、家主の坂井に、坂井の弟とその友人との食事に誘われ、坂井の弟の友人が安井であると知ったところで終わります。
続く第十七章は、次の文から展開していきます。
宗助とお米の一生を暗くいろどった関係は、二人の影を薄くして、幽霊のような思いをどこかにいだかしめた。彼らは自己の心のある部分に、人に見えない結核性の恐ろしいものがひそんでいるのを、ほのかに自覚しながら、わざと知らぬ顔に互いと向き合って年を過ごした。
夏目漱石『門』,角川文庫,1951年初版,186頁
ここでの「結核性の恐ろしいもの」が何を表しているかというと、
安井を裏切ったという罪の意識
であると考えます。
宗助は、この罪の意識を長年自覚しながら、直視するのを避け続けていた節があります。
宗助は、『三四郎』の三四郎や『それから』の代助と比較して、行動範囲が狭く、ごく限られた人々としか交流を持っていません。
非常に閉じた世界の中で描かれる日常は、宗助の逃避の姿勢そのものを表しているように感じられます。
しかし、安井の消息を偶然知ったことにより、宗助は罪の意識と向き合わざるを得ない精神状態に追い込まれます。
罪の意識から生じる心の圧迫や苦しみから逃れるため、人生観そのものを変える必要があると考えた宗助は、鎌倉の禅寺に赴き、参禅します。
※入室参禅とは
修行者が師家(一般の修行僧に対して、禅の修行を終えて修行僧を指導する力量をそなえた者を指す尊称)の室で指導を受けること。
修行者は公案(修行のための禅の問題)を受け、これに対する見解を求められる。
宗助は「父母未生以前本来の面目」という公案(自分の父親や母親が生まれる前のあなたは何者であったのか?という問い)を授けられますが、結局悟りを得ることは叶わず、宗助は以下のような考えを持ちます。
自分は門をあけてもらいに来た。けれども門番は扉の向こう側にいて、たたいてもついに顔さえ出してくれなかった。ただ、
「たたいてもだめだ。ひとりであけてはいれ」と言う声が聞こえただけであった。(中略)
彼は後を顧みた。そうしてとうていまた元の路へ引き返す勇気をもたなかった。彼は前をながめた。前には堅固な扉がいつまでも展望をさえぎっていた。彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないですむ人でもなかった。要するに、彼は門の下に立ちすくんで、日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。夏目漱石『門』,角川文庫,1951年初版,224頁~225頁
参禅さえすれば人生観が変わって、心の圧迫や苦しみから解放されると信じていた宗助ですが、人生観はあくまで自分の力でしか変えられません。
そして、心の圧迫や苦しみに直面した以上、罪の意識から逃避していた頃に引き返すこともできません。
忘れることも、乗り越えることもできず、慢性的に経過する結核のように巣くう罪の意識を、生涯を終えるまで抱えていくしかないという結論に達するのです。
『門』の最後のシーンでは、再び宗助とお米の会話が描かれますが、春の到来を喜ぶお米に対して、宗助は「じきまた冬になる」と返します。
罪の意識から生じる心の圧迫や苦しみから、真に救われることはないと自覚した宗助は、心の苦しみが今後も繰り返されることを予期しており、冬の到来を口にしているのです。
作品冒頭と最後では、縁側にいる夫婦の会話という似た構造が描かれますが、罪の意識から逃避し、今そこにある日常だけに目を向けようとしていた宗助は、最後のシーンではもう存在しないのです。
『門』ー感想
・漱石の参禅体験と鎌倉円覚寺
帝国大学を卒業し高等師範学校の英語教師をしていた漱石は、極度の神経衰弱を患い、明治27年の暮れから正月にかけての約十日間、鎌倉円覚寺の帰源院に滞在し、参禅をしています。
参禅を終えて下山した漱石が友人にあてた書簡によると、漱石自身もまた、これをものにできなかったようです。
『門』は、漱石の実体験を色濃く反映した作品であったと窺えます。
この他、明治41年に発表された漱石の『夢十夜』の中にも、参禅を題材にした作品があります。(詳しくは『夢十夜』第二夜の記事を御覧ください)
-

-
参考『夢十夜』「第二夜」ラストで侍は悟ったのか?
『夢十夜』は夏目漱石著の短編小説で、明治41年から朝日新聞で連載されました。第一夜に続き、第二夜も「こんな夢を見た」という書き出しで始まりますが、第一夜の幻想的な愛の話とは打って変わり、第二夜は参禅の話となっています。ここでは、『夢十夜』第二夜のあらすじ・解説・感想までをまとめました。
続きを見る
参禅体験は、漱石の人生観、文学観に大きな影響を与えた出来事だったと思われます。
また、『門』で宗助が訪れた鎌倉の禅寺は、情景描写の一致から、漱石が参禅をした円覚寺がモデルになったと考えられます。
私も趣味で何度か北鎌倉を旅行し、円覚寺に参拝した経験が数回あります。
威厳を感じる立派な山門が印象的で、境内に残る中世の雰囲気に、ただただ圧倒されました。
漱石が『門』を発表したのは、現代から百年以上も前ですが、歴史を感じさせる境内は、漱石が参禅した当時から寸分変わらずそこにあったのだろうと思うと、密やかな興奮を覚えます。
このように、『門』は様々な角度から、その世界を楽しめる小説です。
・後期作品に連なる愛とエゴイズムのテーマ
『門』の宗助とお米は、同じ「結核性の恐ろしいもの」を抱えていますが、これがどのような苦しみとなって発現しているかは、それぞれ異なります。
宗助は罪の意識から起こる心の圧迫や苦しみを感じています。
一方でお米は、安井を裏切った罪が元で子供ができないと考えており、罪そのものというより、罰への苦しみを感じているようです。
夫婦二人きり、互いの存在だけを拠り所にして成立した野中夫婦でさえ、同じ苦しみを共有しているとは言い難い状況です。
宗助の苦しみは宗助にしか分かりえないのです。
漱石前期三部作はいずれも愛を題材の一つとしており、『門』は結ばれた後の夫婦を描いていますが、私はここに人間存在の孤独さを感じてなりません。
後期の漱石文学では愛と孤独、エゴイズムの追求が進んでいきますが、これに繋がっていくテーマを『門』に見出すことができると思います。
以上、夏目漱石『門』のあらすじ・解説・感想でした。